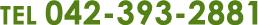「ヘルプマーク」
2025.10.03
ここのところ、「ヘルプマーク」を目にする機会が増えた気がします。
白色の十字とハートがデザインされた赤いカードです。バッグやリュックなどにつけているのをよく見かけます。
バスや電車の中でもよく目にします。それだけ使用する人が増えているのと同時に、よく目立つようにデザインされているともいえるでしょう。
「ヘルプマーク」は、外見からだけでは分かりづらい病気や障害、困難を抱えている方が、例えば、電車で席を譲ってもらう、困ったときに声をかけてもらいやすくなるなど、周囲に支援や配慮を求めやすくなるために考案されたものです。
見た目だけではわからない妊娠初期の方や心臓病などの方、病気の治療中で急に体調を崩す恐れのある方や、精神に障害を抱えている方などが対象とされています。
確かに有用です。
しかし一方で、精神に障害を抱えている方の中には「ヘルプマーク」を使用することに戸惑いと躊躇を感じている方がいるのも事実です。
それは、これまでのあまりにも長い間、「精神疾患」「精神障害」に対し負のレッテル貼りが続いてきた歴史があるからです。
「ヘルプマーク」をつけることが、障害に対する新たなレッテル貼りになるのではないか。
「ヘルプマーク」をつけて助けや配慮を期待しても、逆に遠巻きに、偏見の目で見られてしまうのではないか。
このような不安・恐れ、葛藤から「ヘルプマーク」を遠ざけている方がいるのも事実です。
突き詰めると、精神科医療の歴史の中で常に大きな課題であった、そして今でも大きな課題である「スティグマ」(烙印)の問題にぶつかってしまいます。(今回のブログ記事では、スティグマについて詳述することはしませんが)
スティグマを軽減する社会、スティグマを生み出さない社会にしてゆくために、私たちにできることは何なのか。
「ヘルプマーク」の使用が増えてゆく現実は、あらためて社会的スティグマについて考える機会を与えてくれているようです。
前向きに考えるなら、それだけでも「ヘルプマーク」の意味は大きいといえるのかもしれません。
困っていますというサインを出す人に、ごく普通に手を差し伸べることができる、そのように「ヘルプマーク」が使用されると良いのですが。
精神科医 野瀬 孝彦