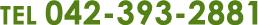ストレス時代をたくましく生き抜く ①ストレスってな~に
2025/11/19
現代人は、変化の速い社会の中で時間に追われ、複雑な人間関係に悩まされ、多くのストレスを抱えていると言われていて、 日常生活の中でも、“ストレス”という言葉はとても気軽にいろいろな場面で使われています。例えば、「最近ストレスがたまっている」とか「運動でストレス発散しよう」などのように。でも、あまりに幅が広すぎて、ストレスっていったいなんなの?と思ったのでちょっと調べてみました。もともとこの言葉は物理学で使われていて、「外からかかる力による物質の歪み」を意味していたのですね。この言葉を医学領域に取り入れてストレス学説を提唱したのがカナダの生理学者であるハンス・セリエ博士(1907-1982)です。博士は生体に作用する外からの刺激に対して、体に生じたひずみ(生体の非特異的な反応)の総称をストレス状態と定義しました。そして、外からの刺激に対するからだやこころの反応のことを“ストレス反応”と呼び、その反応を生じさせる刺激(ストレスの原因)のことを“ストレッサー”と呼びました。
現在一般的に用いられているストレスはこの両方の意味を含んでいるようです。つまり、ストレスとは外部環境の種々の要因が変化したとき、それが刺激となって生体に様々な機能変化が起こった状態ということになります。ストレスの原因としては、物理化学的(熱、音、放射線、化学物質、酸化還元状態の変化など)、生物学的(感染、寄生虫など)、精神的(緊張、不安、恐怖など)なものなどが挙げられています。多種多様です。また、これらの刺激を受けて変化する生体機能も様々です。きわめて日常的に共通に体験される精神現象であると同時に、筋肉の緊張や不眠などのさまざまな生理的変化をともなった身体的現象でもあります。重要な特徴として主観的・相対的であることが挙げられます。
看護部顧問 坂田 三允
高市政権誕生とOTC類似薬
2025/11/05
難産の末、2025年10月に高市早苗さんが総理大臣に選出され新しい政権が誕生しました。日本で初めての女性の総理大臣です。期待度も大きいようです。
とはいっても、物価高対策をはじめとして、直面する課題は山のようにあります。期待を裏切らない総理であってほしいものです。
その、山のようにある課題の中で、医療の現場で働く私の視線は、その中でも医療・社会保障制度の「給付と負担の見直し」というテーマに、自然に向いてしまいます。
保険料の軽減、医療費の抑制、セルフメディケーションの推進のため、「OTC類似薬を保険適応から除外して、自己負担とする」方向で議論されているというところです。
確かにこの議論は、以前からなされていました。
OTC類似薬とは、「市販薬に(成分が)近い処方薬」のことです。(ちなみに、OTCとは、一般の市販薬のことです)
簡単に言ってしまうと、ドラッグストアでも売っているような、鎮痛剤やアレルギーの薬、胃腸薬などは病院で診察を受けて保険で処方箋を出してもらってはいけない。保険を使わず自分でドラッグストアや薬局で自己購入しなさい、ということです。
確かに、このように徹底してしまえば、直接ドラッグストアや薬局へ行く人が増え、病院へ行く人は減る。そうすれば医療費は削減され、保険料も下がる。理論的にはそうなります。
更に、このような考え方は、“セルフメディケーション”の理念とも一致します。
セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)の定義では、「自分自身の健康の維持・改善・疾病予防のために、自己の判断で医薬品などを適切に使用すること」となっています。
厚生労働省もこの流れを押しすすめてきました。セルフメディケーション税制も2017年に導入されています。しかし、浸透度・実際の利用などはまだまだ課題が多いようです。
一方で、この考えに強く反対する意見もあります。
軽症だろうと自己判断して市販薬を使用し医療機関を受診しなかった結果、重症化するケースを見落としてしまう可能性がある。また、所得の低い人たちや高齢者、慢性の病気を持っている方の経済的負担が逆に増加してしまう、などです。
確かに、花粉症などのアレルギーの場合、保険診療で薬を処方してもらうよりも、薬局で購入するとなると、かなり高額になってしまいます。
また、アレルギーだろうと思って市販薬を飲み続けてもなかなか改善せず、医療機関を受診したらアレルギーではなかった、などということもよくあることです。
しかし、ちょっとした鼻かぜや頭痛などでは市販の薬で済ませている人が多いのも、また事実です。実際、ドラッグストアには、選ぶのに困るほどの薬が陳列されています。それくらい需要があるというのも事実です。
さあ、新しい政権は、この課題をどのように処理するのでしょうか。非常に大きな課題であると思います。
最後になってしまいましたが、精神科領域の薬(抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬など)にOTC医薬品は基本的には存在しません。
精神科医 野瀬 孝彦
~モチベーションマネジメント~④「良質なモチベーションは行動の後にしか発生しない」
2025/10/22
目標が設定できない私にできることをさがしていたら、「いつもモチベーションをアップする必要はない」という言葉が目に飛び込んできた。さらに「当たり前ならばモチベーションをアップする必要はない」やることが習慣になっていれば、結果は自然についてくる。なるほど。確かに。
さらに、行動する前の動機づけにモチベーションが必要というのはおかしい。というのもあった。モチベーションというものは天から降ってくるものではなくて、どっかから湧いて出るものでもなくて、順番でいうと行動が先にあって、ちょっとした結果があって、その結果がもたらすものがモチベーション。
確かに、何かやらなければならないことがあって、最初は「めんどうだなぁ」とか「いやだなぁ」とか思いつつやり始めると、いつのまにかいやな気持はどこかに行って、なんとなく、めんどうなことを楽しんでやりおえることってあるなぁと思う。クレペリンは、「何か作業を始めると、だんだん脳はその作業に合わせてやる気を出していく」それを「作業興奮」と名付けたのだそうだ。
暑くなる前に1時間だけと思って始めた草取りを2時間以上続けることもあるもんなぁと思う私。一応きれいになった庭を眺めるのはいいもんだ。満足感もあるしなぁ。「下手な考え休むに似たり」考えるより体を動かせということかな。
看護部顧問 坂田 三允
「ヘルプマーク」
2025/10/03
ここのところ、「ヘルプマーク」を目にする機会が増えた気がします。
白色の十字とハートがデザインされた赤いカードです。バッグやリュックなどにつけているのをよく見かけます。
バスや電車の中でもよく目にします。それだけ使用する人が増えているのと同時に、よく目立つようにデザインされているともいえるでしょう。
「ヘルプマーク」は、外見からだけでは分かりづらい病気や障害、困難を抱えている方が、例えば、電車で席を譲ってもらう、困ったときに声をかけてもらいやすくなるなど、周囲に支援や配慮を求めやすくなるために考案されたものです。
見た目だけではわからない妊娠初期の方や心臓病などの方、病気の治療中で急に体調を崩す恐れのある方や、精神に障害を抱えている方などが対象とされています。
確かに有用です。
しかし一方で、精神に障害を抱えている方の中には「ヘルプマーク」を使用することに戸惑いと躊躇を感じている方がいるのも事実です。
それは、これまでのあまりにも長い間、「精神疾患」「精神障害」に対し負のレッテル貼りが続いてきた歴史があるからです。
「ヘルプマーク」をつけることが、障害に対する新たなレッテル貼りになるのではないか。
「ヘルプマーク」をつけて助けや配慮を期待しても、逆に遠巻きに、偏見の目で見られてしまうのではないか。
このような不安・恐れ、葛藤から「ヘルプマーク」を遠ざけている方がいるのも事実です。
突き詰めると、精神科医療の歴史の中で常に大きな課題であった、そして今でも大きな課題である「スティグマ」(烙印)の問題にぶつかってしまいます。(今回のブログ記事では、スティグマについて詳述することはしませんが)
スティグマを軽減する社会、スティグマを生み出さない社会にしてゆくために、私たちにできることは何なのか。
「ヘルプマーク」の使用が増えてゆく現実は、あらためて社会的スティグマについて考える機会を与えてくれているようです。
前向きに考えるなら、それだけでも「ヘルプマーク」の意味は大きいといえるのかもしれません。
困っていますというサインを出す人に、ごく普通に手を差し伸べることができる、そのように「ヘルプマーク」が使用されると良いのですが。
精神科医 野瀬 孝彦
~モチベーションマネジメントのこと~③「目標を設定する」
2025/09/19
やる気を出すもとは自分の中にあるらしいということはわかったけれど、ハテ?
困ったときのGoogleさん頼み。モチベーションと入力してみたら、出てくる出てくる!!
部下のモチベーションを上げるには・・・などというものが一番多かったかな。でも、これは私には関係ない。私が知りたいのは、自分で自分のモチベーションを上げるにはどうすればいいのということなのだから。というわけでそれらしきことが書かれているものを探した。
その1。まず、目標を設定することだとある。目標を細分化する。しかも明確な達成基準があることが必要で、さらにその目標が自分にとって魅力的であり、目標レベルが適切であること。達成基準が五分五分の時モチベーションは最も高まるのだそうだ。さらに、たとえば、周囲の人に目標について話すなど。外的条件でしばりをかけ、強制的にやらざるを得ないようにする。目標を達成したときどんな感情が湧き上がってくるかイメージする。お説ごもっともなのだが、なんとなくすっきりしない。
たとえば、今の自分に当てはめて考えてみると、我が家は中古住宅で、前の持ち主が作られた庭がなんとも私の趣味に合わない。狭い空間なのにしだれ梅と百日紅、月桂樹、雪柳がドンと居座っている。手入れをしていないものだから、好き勝手に伸びて、縁側でジジババが茶をすすりながら眺めるイメージからは程遠い。腰の曲がったばあさんにできることといえば、せいぜい木の下に生えている雑草をとることくらいだ。目標が遠大すぎて、設定できない。
看護部顧問 坂田 三允
処方が間違っている
2025/09/05
精神科薬物療法は根拠のない出鱈目が多く、節操のない多剤多量処方による薬漬けが横行している、という非難が昔も今も方々から寄せられる。あながち事実無根の誹謗中傷ではないと感じる一方で、多くの精神科医はそこまでひどくはないですよ、とか、大変な患者の薬剤調整は一筋縄ではいかんのですよ、とつい言い訳が漏れ出そうにもなる。
この手の糾弾を浴びるのはひとり精神科医のみであり、他科の医師にはほとんど無縁ではなかろうか。むろん、どの科においても診断や病態を捉え損ねて薬剤選択を誤る、ということはあろう。無知に基づく誤りやバイアスによる逸脱は論外として、精神科においては診断や病態を正しく評価できていてもなお、薬剤選択や処方量がおかしくなることがありうることは、特筆すべきだろう。知識も経験も豊富なひとかどの精神科医にあっても、時として、処方変更を繰り返して一向に定まらない「彷徨的処方行動」1に陥り、患者が要求するがままに処方し続ける「白衣を着た売人」2に堕すことがありえるからには、事はそう単純ではない。
我々が処方する向精神薬が、主として精神症状を標的とし、脳=中枢神経系を媒介して心=体験世界を変化させる薬理作用をもつことは、その原因のひとつかもしれない。この構造ゆえ、効くと思い込めば効く(プラセボ効果)、効かぬと思い込めば効かぬ(ノセボ効果)、の主観的変数が大きく介在せざるをえず、患者のみならず治療者も、精神行動上の変化を主観的・間主観的に捉えて評価するほかなく、身体科薬物療法ような血液検査や画像による客観的な効果判定は不可能に近い。よく効きました、という安堵の表情を見れば少量単剤で済むものが、全然効きません、という焦慮の表情が続けば多剤多量に流されかねない。重い精神病症状や逸脱行動が遷延すれば、医師の焦りから無差別爆撃的な多剤高用量処方を招く恐れもある。
それがゆえにか、精神科医は向精神薬を単なる物質として患者に投与するのではなく、意識的にであれ無意識的にであれ、様々な想いを言葉とともに薬に乗せて差し出すようになる。それは、少しでも良くなりますようにという願いや祈りであることがほとんどだが、時には、いい加減にしてくれという陰性感情のこともあろう。薬物療法家の立場からすれば、こうした心理的夾雑性はできる限り排したいだろうし、精神療法家の立場からすれば、逆に薬という物質的夾雑性を邪魔に感じるかもしれない。しかし、実地臨床においてはあくまで両者のアマルガムしかありえない。
このことは、医師-患者の関係性そのものが薬効に大きな影響を及ぼすことにも通じる。身体治療と比較すればわかりやすい。例えば外科医であれば、いかに愚劣でも手術の腕前が超一流の方が、人格者ではあるがぶきっちょで手術下手よりも、明らかに治療的と言える。一方、精神科医であれば、少なくとも患者から信を置かれるに足るだけの誠実さや礼容等、その人間性が治療に少なからぬ影響を及ぼし、ひいては薬効をも左右する。安定した治療関係では処方はシンプルかつ少量に傾き、不安定な治療関係では多剤多量に傾きやすい。
さらに、精神科薬物療法は医師から患者へと一方的に投与されるものではなく、医師と患者が共同作業により産み出していく合作、という含みが強くなる。アレでもないコレでもない、と二人三脚で長い時間をかけて作り上げた処方レシピは、医師の存在とも相俟って、患者にとってなくてはならない支えとなる。さながら、長年連れ添った妻の手料理が、夫の日々を無言の裡に支えているように。
反対に難渋する治療においては、こじれた夫婦関係のように、いくら対話を積み重ねても軋轢が修復できず、溝が広がることもある。気づいた時には、患者もろとも多剤大量処方の海の中へ投げ出され、漂流している。そしてある日、増えども増えども一向に改善しないことに絶望した患者がオーバードーズし、救命救急外来に運ばれる。情報提供を求められた主治医は、自らの手による破廉恥極まる処方にあらためて直面し、愕然として天を仰ぐ。後日、患者にとっては行きずりにすぎない精神科医がコンサルテーションした結果、見事に減薬されてエレガントな処方となり、憑きものがとれたようにすっきりとして舞い戻ってきた彼女と対面した主治医は、茫然として再び天を仰ぐ。
だから、そのような処方を見つけたら、どうか勇気をもって声を上げてほしい。「センセー、その処方は間違ってます!」と。
副院長 栗田 篤志
1 中井久夫 2000 『中井久夫選集 分裂病の回復と養生』星和書店
2 松本俊彦 2021 『誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論』みすず書房
(1895字)
~モチベーションマネジメントのこと~②
2025/08/06
モチベーションとは(行動などに対する)動機づけや刺激、やる気、意欲である。人が一定の方向や目標に向かって行動し、それを維持する働きともいえる。モチベーションは、ドライブ(動因、駆り立てるもの)とインセンティブ(誘因、行動を誘発するもの)という2つの要素から成り立つ。つまり、モチベーションを向上させるには、誘因か動因、あるいはその両方が必要ということになる。
(ふむふむ)
誘因は外部から報酬を与えて、モチベーションを向上させようとする方法で、外発的動機づけといわれる。特別ボーナスが出ることや、ほめられることがこれにあたる。
(う~んこれは余り期待できないぞ)庭の草が無くなっても誰も感謝などしてくれないだろうし、美味しい食事を作っても当たり前だものなぁ。
それに対して動因は自らの意思で主体的に目標を立て、目的に向かって行動を起こすような方法で内発的動機づけといわれる。
たとえば「衝動買い」はディスプレイが誘因になり、「買いたい」という動因が引き起こされた結果として生じる。また、「買いたい」という強い動因があれば、ディスプレイという誘因がなくても買いに行く行動は起こるが、いくら強い誘因があっても動因が生じなければ行動は起きない。(なるほど)
つまり、モチベーションをあげる(やる気を出す)もとは自分の中にあるということだ。
看護部顧問 坂田三允
毎日を元気に過ごす ~モチベーションマネジメントのこと~①
2025/07/22
片道2時間半の通勤が大変だと思うようになって、お仕事を減らした。長時間家にいることになって念願の「晴耕雨読の自由な生活!!」のはずだった。ところが、「ねばならぬこと」がなくなってしまったら、いやいや「ねばならぬこと」がないわけではないのだがそれこそ、締め切りのないいつでもできることばかり。生来怠け者(だったのかなぁ)の私は、だらだらとメリハリのない毎日を過ごすようになってしまった。何となく、元気いっぱいと言うわけにはいかなくなった。
元気が出ることってどんなことだろう。嬉しいことや楽しいことがあったとき?たとえばお仕事をしていて特別ボーナスが支給されることとか?それは「思いがけないことで嬉しいですね~」でも、仕事を辞めたらそんなことは起こらない。自分のしたことが高く評価されて褒められることや感謝されることなども、元気の元になるかもしれないけど、庭の草取りをしたからと言って、誰かがほめてくれるわけもないし、感謝されるわけでもない。楽しいことを計画していて、それが近づいてくるとなんだか浮き浮きして元気が出てくるということもあるなぁ。
楽しいことを計画する!!楽しいことはそれが終わってしまうと、「祭りの後」の虚しさが漂ったりはするけれど、それでも次の楽しみを計画すれば、再び元気になる。何より他者まかせではなく、自分の好きなようにできることがよい。いつも鼻先にニンジンをぶらさげないと走れない馬のようだけど、それで元気を維持できるなら、それはそれでよい。
というわけで、以前にちょこっとお勉強したことがある「仕事に対して元気に取り組んでいくための方法」であるといわれる、モチベーション・マネジメントのことを再学習(?)してみようと考えた。
看護部顧問 坂田三允
ハラスメントについて
2025/07/02
今、いろいろな「ハラスメント」が問題になっています。お客さんの立場からの過度な要求が「カスタマー・ハラスメント」と言われます。病院では「ペイシェント・ハラスメント」とも言いますね。患者さんご本人からのものもありますし、ご家族など関係者からのものもあります。
患者さん等から御不満の声などが寄せられる場合、もちろん病院が正しいばかりとは言えません。私たちが考え方ややり方を改めなければならないことも、実は少なくありません。当院もいろいろなルートで検討し、改めるべきところは改めてきているつもりです。
但し、すべてにお応えできるわけでもないのも、またご理解いただきたいところです。寄せられるご要望は人手があれば解決できるものが多いですが、それには人件費がかかります。病院は診療報酬で収入が細かく規定されており、営業努力などで増収を図ることには限界があります。むやみに人を増やすことができません。また、熟練した専門家には限りがあり、たやすく採用できるわけではないことも加わります。健康保険にはいろいろ不合理な制約もあって、求められた医療を行うことが医学的には妥当と考えられてもそれができないこともあります。
また、医療でできることについての理解が、ご本人やご家族と私たちとの間で差があり、そこが問題になることもあります。
実は、夜間や休日など、人が少ないときに、電話や対面で、患者さんやご家族から職員に、長時間のお話をされることが少なくなく、病院の大きな負担になっています。繰り返すように、私たちの対応に問題があり、当然のご要望のこともあります。しかし、そうではないこともあります。一般企業でカスタマーセンターのようなところがあるところもありますが、そういうところは多くは電話受付時間が平日日中ですし、電話をしても「ただいま電話が大変混み合っております・・・」となって待たされることがしばしばです。しかし、病院は、急を要する患者さんがいらっしゃるので、電話の24時間対応は当たり前で、職員も24時間誰かはおりますので、「逃げられない」立場にあります。このあたりも問題を複雑にしていると感じます。
さらに問題なのは精神科に固有の事柄です。特に患者さんご本人が、コミュニケーションに苦手な部分があることがあります。この場合は病院としてはそれに時間をとって対応することが求められると思いますが、大声、威圧などが加わって、ハラスメント類似の問題に至ることもあります。最近でも病院内での暴力が問題になっており、病院内はもとよりどこであっても暴力が許されないことは確かですが、暴力自体が症状である患者さんがいらっしゃることもまた事実で、これは「ハラスメント」として扱うよりも治療の対象としてみなさなければならないこともあります。こうした見極めを、私たちは日々求められています。
いずれにしても、なるべく良好な関係のもと、最善の医療を行い、患者さん、ご家族に満足いただける結果に導くことが最良であることは論を待ちません。当方も努力しているつもりですが、不充分な点についてはお聞きして改める用意があります。患者さん、ご家族の皆様におかれましても、病院の事情をご理解いただきますよう、この場を借りてお願いいたします。
院長 中島 直
人間関係って難しい(-_-;); コミュニケーションについて思うこと②
2025/06/18
看護は多くの人とのかかわりなしにはできない仕事である。看護師と患者の関係は、看護師を通して進展していく。
看護師としては、患者さんの情報を得るのは仕事のうちでもあるのだが、患者さんには、答えたくないことやときがある。ご家族は何人ですかと聞いたとき、嫌な顔をしたら、言いたくないことなのだな、と察することも一つの情報だろう。患者さんには鎧をつけている方もいれば、高い壁のある人もいる。「う~ん、めんどうくさいなぁ」と思わないでもない。だけど、鎧が1つずつ取れるのをゆっくりと待つしかないのである。無理にこじ開けると鎧がもっと強固になることの方が多いからだ。
看護という仕事に限らず、私は相手との関係を3つの階層の分類でとらえることにしている。第1層は、自分の家族だったり、大切な人 自分にとって重要な他者とのかかわり。第2層は、仲のよい友達。そして第3層はビジネスライクのおつきあいの人。
1層の人は別として、人との関係は、まず3層から始まる。ビジネスライクなかかわりの中で、何かのきっかけで、家族のことや趣味などの話題が出て、同調したり共感するようなことがあって、距離が少しずつ縮まっていく場合もある。すべての人間関係を3層から2層に発展させていく必要はないし、してはならない場合の方が多いかもしれない。けれど、3層の人の話も興味をもって聞いていると、時として、相手の気持ちがわかることがある。一線をひいての関わりであっても、相手に幸せな顔になってもらいたいという気持ちが生まれてくることもある。このときは、相手のためになりたい自分を楽しめばよい。あとで黒バックのような話になるかもしれないが、なっても後悔しない。自分がしたことは、自分で決めたことだから。
看護部顧問 坂田三允