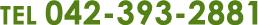傍らで共にあること
2025/02/19
うれしい体験もありました。何か行為をして、それが患者さんにとってほんとによかったのかどうかということはなかなか確かめることができません。精神科でケアを評価するのはとても難しい。患者さんは喜んでくれるわけでもないし、「何しに来たのよ、あっち行ってよ」なんて言われながらその場にいることだって必要なわけですから。そんな中で、長い六十何年の間で唯一の体験だと思うのですが、とても患者さんに感謝された体験があります。
その人はボストンバッグ抱えてホールに出てきて、ボストンバッグの中のものをまき散らし始めました。しばらく「なんでこんなことをしているのだろう」と思って見ていたのですが、なんとなく彼女のそばにいってみようかなという気持ちになったので、横に座って患者さんが放り出したものをたたんで重ねていくという作業を無言で続けました。彼女が広げる、私がたたむということを3、4回繰り返したあと、最後に私がたたんだのをボストンバッグに詰めて彼女は部屋に戻っていきました。なんだったのだろうとずっと思っていたのですが、分かりませんでした。2年か3年たってからのことです。外来でバッタリ彼女に会いました。そうしたら「坂田さん」って抱きついてきて「坂田さん、あのとき一緒にいてくれたよね。うれしかったよ」と彼女が言うのです。一言も話していないんです。お互いに。ただ、無言で出して入れて、出して入れてということを繰り返していただけなのです。
そのときに、言葉じゃないんだということがすっとわかったのです。存在、そばにいること、ともにあることの意味のようなものでしょうか。そのときのことは、なかなか言葉では表現できないのですが、何かそこにいてあげたくなって、いることが苦痛ではなくて、最初の始まりは「なんでこんなことするんだろう」という思いでしたけれど、そのやりとりをしている間、不快でなかったことは確かです。彼女が快であったかどうかは分からなかったのですが、その彼女の一言を聞いて、あのときやっぱり彼女も不快ではなかったんだっと分かって、こちらが不快じゃないときというのは、もしかしたら相手も不快じゃなくいてくれるときなのかもしれない。そういう2人がともにいることで時間がつぶせたら、それはそれですてきなことかもしれないということを学びました。ですから、コミュニケーションは言葉ではないということもとても大事なことのような気がしています。
看護部顧問 坂田 三允
院内感染対策のこと
2025/02/05
新型コロナ(COVID-19)の流行があり、普段から病院の面会や外出等に制限をもうけている病院が多くなっています。当院も実は、若干ですが時間等の制限をしています。これがおかしいという議論はあり、一理あります。あまり外部との交流を持たず、入退院も少ないような精神科病院で、コロナを口実により一層閉鎖性を強めているところがあり、そういうのは大きな問題です。しかし、面会が感染症を持ち込まれる契機の一つであることは確かです。これまで当院は何度もクラスターを経験しています。その多くは原因が不明で、推測できるもののうち一番多いのは職員由来、次が入院患者さん由来で、面会者からと思われるものは少ないですがやはりあります。
クラスターは、コロナに不顕性感染や潜伏期、検査での偽陰性等があることで、やむを得ないところがあります。しかし、一度これが起こると、患者さんたちを危険にさらしますし、行動の制約も伴います。職員にもうつりますので、勤務者が減り、病棟業務に支障が出ます。入院をお受けできなくなると、いざというときに頼ってきてくださっている地域の方にも迷惑が掛かります。病院の経営としても、膨大な物品や廃棄物処理が必要になり、支出が増えます。できるだけ予防したいというのは正直なところです。
しかし、当院は、入退院についてはできるだけ止めない、というふうにやっています。クラスターの真っ最中は入院も退院も制限せざるを得なくなることがありますが、それ以外はなるべく制限せず、特に退院のために必須であるような外出・面会・会議等は行うようにしています。今後も皆さんのご要望をお聞きしつつ、よりよい方法を検討していきます。何卒ご理解・ご協力をいただきたく、この場を借りてお願い申し上げます。
院長 中島 直