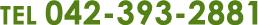高市政権誕生とOTC類似薬
2025/11/05
難産の末、2025年10月に高市早苗さんが総理大臣に選出され新しい政権が誕生しました。日本で初めての女性の総理大臣です。期待度も大きいようです。
とはいっても、物価高対策をはじめとして、直面する課題は山のようにあります。期待を裏切らない総理であってほしいものです。
その、山のようにある課題の中で、医療の現場で働く私の視線は、その中でも医療・社会保障制度の「給付と負担の見直し」というテーマに、自然に向いてしまいます。
保険料の軽減、医療費の抑制、セルフメディケーションの推進のため、「OTC類似薬を保険適応から除外して、自己負担とする」方向で議論されているというところです。
確かにこの議論は、以前からなされていました。
OTC類似薬とは、「市販薬に(成分が)近い処方薬」のことです。(ちなみに、OTCとは、一般の市販薬のことです)
簡単に言ってしまうと、ドラッグストアでも売っているような、鎮痛剤やアレルギーの薬、胃腸薬などは病院で診察を受けて保険で処方箋を出してもらってはいけない。保険を使わず自分でドラッグストアや薬局で自己購入しなさい、ということです。
確かに、このように徹底してしまえば、直接ドラッグストアや薬局へ行く人が増え、病院へ行く人は減る。そうすれば医療費は削減され、保険料も下がる。理論的にはそうなります。
更に、このような考え方は、“セルフメディケーション”の理念とも一致します。
セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)の定義では、「自分自身の健康の維持・改善・疾病予防のために、自己の判断で医薬品などを適切に使用すること」となっています。
厚生労働省もこの流れを押しすすめてきました。セルフメディケーション税制も2017年に導入されています。しかし、浸透度・実際の利用などはまだまだ課題が多いようです。
一方で、この考えに強く反対する意見もあります。
軽症だろうと自己判断して市販薬を使用し医療機関を受診しなかった結果、重症化するケースを見落としてしまう可能性がある。また、所得の低い人たちや高齢者、慢性の病気を持っている方の経済的負担が逆に増加してしまう、などです。
確かに、花粉症などのアレルギーの場合、保険診療で薬を処方してもらうよりも、薬局で購入するとなると、かなり高額になってしまいます。
また、アレルギーだろうと思って市販薬を飲み続けてもなかなか改善せず、医療機関を受診したらアレルギーではなかった、などということもよくあることです。
しかし、ちょっとした鼻かぜや頭痛などでは市販の薬で済ませている人が多いのも、また事実です。実際、ドラッグストアには、選ぶのに困るほどの薬が陳列されています。それくらい需要があるというのも事実です。
さあ、新しい政権は、この課題をどのように処理するのでしょうか。非常に大きな課題であると思います。
最後になってしまいましたが、精神科領域の薬(抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬など)にOTC医薬品は基本的には存在しません。
精神科医 野瀬 孝彦