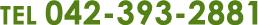「夏に原稿依頼を受け完成したら、ちょっと季節が」
2024/12/02
とても暑い夏でした。“猛暑”という言葉を一日に何度聞いたでしょう。そしてこの“猛暑”が原因で起こる“熱中症”も、耳にしない日がないくらいでした。
“猛暑”=“熱中症”が、普通に日常会話の話題として、場合によっては挨拶のように使われるようになってしまいました。
“熱中症”とは、高温多湿が原因で、身体の水分や塩分のバランスが崩れてしまう状態です。
更に進んで体温の調節機能が崩れてしまうと、体温が上昇した状態が続いたままになってしまいます。これはとても危険な状態です。
初期の段階では、身体から水分が減少することにより、脳や筋肉などに十分血液がいきわたらないため、めまいや立ちくらみ、手足のしびれや気分不快感といった症状が出現します。
さらに進行すると、心臓に戻る血液が少なくなり、結果的に、脳や内臓への血流も減少するため、肝臓や腎臓の機能も障害され、吐き気や嘔吐、激しい頭痛、からだに力の入らない脱力状態となり、真っすぐ歩けない状態となります。
この状態が改善されないまま続くと、更に体温が上昇し、脱水と循環不全(身体中の臓器への血流が極端に減少し、機能できなくなった状態)がさらに増悪します。体温が40℃以上に上昇してしまい、脳を含む重要臓器の機能が一層障害され、体温調節が全くできない状態となり、全身がけいれんしたり、意識がなくなる昏睡状態となることも稀ではありません。高齢者で身体の衰弱が激しかったり、身体疾患がある場合は、最悪のケースでは死に至ることもあります。
本来、人間には、少々気温が高くても、あるいは低くても、上手に順応する機能が備わっています。
それは自律神経というシステムです。
自律神経は身体中すべてに張り巡らされ、すべての臓器のバランスを保ち、ストレスや環境の変化に応じて体内環境を微調整しながら一定に維持する役割を担っています。
一言で言ってしまえば、“熱中症”の怖さは、自律神経系の働きを壊してしまい、健全に機能できない状態にしてしまうことです。
この自律神経系の障害は精神の疾患とも深いかかわりを持っています。
季節の変わり目などに精神状態が不安定になる、気分の変動が激しい、睡眠状態が極端に悪くなる、あるいは過眠となるなどは以前から知られています。
また、うつ病や統合失調症、更には認知症の症状にも自律神経系との関係が指摘されています。
パニック障害や“不安障害”では自律神経の症状が顕著に認められます。
自律神経系は心身のすべてに影響を与え、その一方で、心身の内からの、そして外からの“ストレス”に過敏に反応して症状化します。
これからの季節は、むしろ外的な環境の変化が自律神経系に対して“ストレス”となり、精神面での変調として現れることもあります。
自律神経の働きについて知っておくことは、“熱中症”だけではなく、自身の心身の安定にとってプラスに作用するでしょう。
副院長 野瀬 孝彦
「あなたのために」と「私のために」‐②
2024/11/11
引き続き40年以上の前の話ですが、そのときは私が悪いなんて思っていなかったです。躁状態に面と向かっていっちゃいけないなど学んだ記憶はなかったですから、私は真面目に応対したのになんでこんなことになるのよって怒っていました。ですから、次の日、報告して「もう隔離してください」と言いました。主治医は隔離してくれました。でも、そのときに「君のためにするんだからな」と言われたのです。
その意味を私は長い間分かりませんでした。反省もしていませんでした。そしてそのときから、とにかく夜中に起きてくる患者さんには、向こうが何か言う前に追加の眠剤を渡していました。眠れないと言われたわけでもないのに「はい飲んで」と。眠れないのがつらいだろうから患者さんは早く寝かせてあげようと眠剤を渡していたのは、私が大変な思いをするのが嫌だったからにすぎないんだということが分かったのはずいぶんあとのことでした。とても恥ずかしく思いましたし、患者さんに悪いことしたと思います。でも、やってしまったことは取り返しがつかない。後に生かすしかないんですね。
何かの行為をするときには、ほんとにこれは患者さんのためなんだろうか、私のためにやってないだろうかということを吟味しながらやらなければいけないということなのだと思いますし、何かにひっかかりを感じたことを手がかりに自分の行いを振り返ることもとても大切なことだと思っています。
看護部顧問 坂田 三允
災害ヘルメットをかぶった事はありますか?
2024/10/25
今年の8月8日、宮崎県の日向灘沖で最大震度6弱の地震が起き、南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。南海トラフ地震はマグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に70%~80%の確率で起こるといわれている巨大地震です。また南海トラフ地震とは別に首都直下型の地震も同様の確率で起こる可能性があります。いつ起きるかわからない巨大地震に対して私たちはどんな準備や訓練をしておくべきか真剣に考えなければなりません。当院の災害対策チームは2016年5月に発足され、少しずつ準備を進めてきました。緊急連絡網の作成、災害備蓄品の購入、インフラ(電気・ガス・水)の設備確認、そしてBCP(事業継続計画)の作成をしてきました。定期的な訓練としては、一斉情報共有システム訓練、非常食作成訓練をしています。
そして先日、実際に災害備品を取り出して使用する訓練を行いました。災害備品は簡単に組み立てられるような仕組みになっていると思っていましたが、フタを開けてビックリ、なんと腰掛イスすら作れない!どう組み立てるのかわからず、5分以上四苦八苦してしまいました。ただ一度完成させてしまうと、それはもう簡単なのです。次に簡易トイレのテント、広げるのはすぐにできたのですが、今度は折りたためない!!数人のスタッフで色々と試しても結局折りたためず、最後はYouTubeに助けてもらう始末でした。備蓄品は購入して準備完了ではありません。実際に使い方を把握しておくまでが準備です。発災してから、これどうやるの?では手遅れです。昨年に参加した研修で、まず何から始めたらいいか質問したところ、「ヘルメットをかぶる事から始めましょう」と教えていただきました。まずは自分自身の命を守るという意味です。皆さん職場の防災ヘルメットをかぶった事はありますか?是非ともかぶってみて下さいね。
看護部長 村上 朋仁
袴田巖さんの再審無罪確定
2024/10/10
死刑判決を受けていた袴田巖さんの再審無罪が確定しました。時々報道されているのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、袴田さんは釈放翌日の2014年3月28日から2か月間、縁あって当院に入院し、私が主治医となりました。この当時は病院業務や患者さんへの悪影響を防ぐため秘密にしていましたが、2019年にはご本人をはじめ関係者の許可を得て経過を学術誌で報告しました。
入院はもう10年前のことです。当時在籍した職員は、主として弁護士・支援者などへの対応で、普段とは違うことに気を遣って大変でした。これを丁寧にやってくれた全職員に今も感謝していますし、また誇りにも思っています。
袴田さんの示している症状は拘禁反応でした。入院は治療というより袴田さんの身体・精神状態の把握と生活支援体制の準備のためでした。残念ながら入院中には症状が軽快したとは言えませんでした。釈放されてもなお「死刑囚」であったことが大きく、真の改善には「死刑囚」の地位からの解放が必要であると感じられました。
袴田さんや、お姉さんをはじめとした関係の方々の長年の労苦には、かける言葉も見つかりません。私たちも、ごくわずかなものではありますが、役割を果たしたこと、改めて誇りに思います。袴田さんには、今回ようやく真に死刑から解放され、当院の治療ではなし得なかった症状の改善が、少しずつでも実現することを切に願います。
2024年10月10日 院長 中島 直
「あなたのために」と「私のために」‐①
2024/09/20
私たちは患者さんのためにいろいろなことをしているつもりでいます。でも、よく考えてみると、それは病院のためであったり、病棟のルールに縛られているだけのことであったり、私のためであったりすることもまれではないような気がします。少なくとも私は患者さんのためといいつつ、私のためにやっていることがあるなあと思います。
今から40年以上前の話で、これはもう100%、完全に私が悪いのですけれど、躁状態の患者さんと議論をしてエスカレートさせてしまいました。議論をしてと言うと聞こえがいいのですが、議論どころの騒ぎではなくけんかです。
その患者さんが夜、眠るころになって「おなかが空いたから何か食べさせろ」と言ってきました。正面切って「何もありません」と答えました。「ご飯が残ってるはずだろう、おにぎり作ってこい」「ないです」と何度も言い合い、終いには「駅前にこれから車で行ってラーメン食いに行こう」「冗談じゃない」という話になり「さあ、もう寝ましょう」と話を打ち切りました。それで終わったと思っていたのですが、とんでもないことでした。すでに眠りについていた患者さんを全部起こして「何か食い物はないか」って聞いて回ったんです。起こされた患者さんたちに「看護婦さん、何とかしてくださいよ」と言われて、大変な目にあったのです。
看護部顧問 坂田 三允
今日は始業式でした
2024/09/03
今日は当院の院内学級(小平特別支援学校武蔵分教室の一部という扱い、通称「風の学校」)の始業式でした。
当院に学童期の子たちが多く入院するようになり、教育の機会の保障のため、関係各所のご協力のもと、2019年2月に「風の学校」が開設されました。2022年3月に当院が児童思春期病棟を作ったことで、その役割はますます大きくなっています。いろいろな症状や行動上の問題、悩みを抱えている子たちですが、学校では全然違った面を見せることは、私たちにとって驚きであり、また学びでもありました。子たちは成長していきます。病棟では日々いろいろな問題が起きて大変ですが、この成長は、私たちの大きな励みになっています。院内学級は大きな役割を果たしています。先生方が、一人一人の子たちが意欲を続け、また学習効果を上げられるように、日々いろいろな工夫をしています。子たちもそれに応える努力をしています。
始業式や終業式と言っても、ちゃんと椅子に座っていられない子たちもたくさんいるのですが、今日は、なぜかほとんどの子たちが熱心に先生方の話を聞いていました。私も院長として、皆に2学期の間頑張ってほしいというお話をしました。
院長 中島直
患者さんの言動には必ず意味がある‐②
2024/08/30
それから2~3週間後のことです。2人の看護師が後ろからビシッとたたかれて、お湯を掛けられました。その時には入浴のときのことなど忘れておりました。いきなりのことだったので「何?何?」という感じでした。でも、患者さんはその2人(お風呂から引っ張り出した看護師。私はすでに引っ張り出した時に顎を蹴られて舌を噛み痛い思いをしていた)以外には手を出さなかったのです。それで「あ、仕返しなんだ」ということが分かりました。仕返しと言うと言葉は悪いですが、よっぽど嫌だったんだろうなと思ったのです。気の毒なことしたと思います。それはそれとして、もし、お風呂つながりで覚えていなければ、彼女の行為は訳の分からない行為と考えられていたかもしれません。
看護部顧問 坂田 三允
患者さんの言動には必ず意味がある-それは衝動行為ではなかった-①
2024/08/01
統合失調症で強迫行為がとても強く、入浴時にはシャンプーとリンスの大きなボトルと石けんの新しいものを1個使い切るまで出ることができない患者さんがいらっしゃいました。病院にはお風呂が一つしかなかったので、入浴日には男性と女性が途中で交代して入るという方式をとっていました。女性が先に入る日に、その方が交代まであと1時間しかないというときに入浴されました。「あ~、間に合わない」と思ったのですが、毎日入浴できるわけでもありませんし、その方はもともとあまり入浴ができる方ではなかったので、ある意味ではご自分からされるのはよいことでもありましたから、そのまま様子を見ることにしました。1時から3時までが女性で3時ちょっと過ぎから5時が男性という流れの日だったのですが、男性が入る時間になっても上がってこられません。「男性の時間だから出て」「いいですよ、入ってください」「そういうわけにはいかないので出てください」「大丈夫です」「大丈夫じゃありません」というやりとりを何回も繰り返すことになりました。男性もだんだん「風呂に入らせろ」と騒ぎます。「ちょっとごめん、待っててね」と言って、4時、だんだん夜勤帯も近くなります。ずっと待っているわけにはいかないということで、医師とも相談して、看護師3人と医師の4人で毛布を掛けてむりやり引っ張り出しました。
看護部顧問 坂田 三允
看護実習生の受け入れ体制と実習控室一新、そしてプレミアムな指導者
2024/07/26
当院は2012年より看護学生の実習を受け入れています。この11年間で看護大学8校と看護専門学校1校の精神科実習を受け入れ、当院で実習した看護学生は595名にのぼります。私は実習を受け入れ始めた1年目より、実習指導者として一人一人の看護学生とかかわり、共に学んできました。毎年、2名の看護師が実習指導者研修を受講し、少しずつ実習指導者も増員してきました。今年度も6月より看護学生を受け入れ、各病棟の実習指導者も着々と準備を進めています。また、看護学生の実習控室が変わりました。設備も整い、実習記録や学生カンファレンスに集中できる環境が整ったと思います。最後にとっておきの話ですが、当院で実習した看護学生595名のうち1名の看護師が新卒で入職しています。この看護師は今年で4年目となり、実習指導者として活躍が期待されています。いつだって笑顔を絶やさない595分の1のプレミアムな看護師です。後輩たちへも満点の笑顔で指導してくれることでしょう。
看護部長 村上朋仁
大変な患者を引き受けるということ
2024/06/28
当院は重症、難治、治療抵抗性、処遇困難等と称される、いわゆる大変な患者をできる限り断らずに引き受け、地域で支えることを実践している。例えば次のような面々を(いずれも実例に基づく架空のケースである)。
ある女性は恋人と同棲するという妄想に駆られて住居家財の全てを失い、路頭に迷って徘徊し、かかりつけにも入院を拒まれたため当院で引き受け、退院先を調整した。また、ある女性は困難にぶつかると暴力に訴える術が骨がらみとなり、どの医療機関からも拒まれ行政からも排除され、当院に流れ着いた。入院後も他患や看護師への暴言暴力は制御不能で治療は難渋を極めたが、粘り強く支援し、行政とも折衝して何とか地域に棲まわせた。ある男性は酒浸りで身を持ち崩し、家族からも職場からも見放され、身も心もボロボロになってなお断酒できず、入退院を繰り返したが、少しでも生き長らえるよう手を尽くして地域で支えた。また、ある男児は暴言暴力、窃盗、恐喝、性的逸脱、虚言と悪辣の限りを尽くし、家族からも学校からも見捨てられ、一時保護所でも暴れて手が付けられず、当院に入院した。入院後も逸脱行動を繰り返したが、成長を促し続けて一定の安定を得た後、地域へ戻し復学させた。
こうした大変な患者の支援を続けることは、むろん労多くたやすくはない。しかも大変なほど加算がつくということもなく、逆に人手はかかり持ち出しのほうが多いくらいだろう。では、なぜ引き受けるのか。なぜ社会から排除されるべき厄介者にそれほど肩入れするのか、と訝る向きもあろう。なぜならば、彼らは決して私たちの彼岸にいる全く異質な他者ではないからだ、と私は答えたい。彼らの生は、私たちの苦悩や困難の誇張された戯画であり、誰かの支えやたまさかの幸運の積み重なりがなければ陥っていたかもしれないという意味で、私たちの生の陰画(ネガ)である。いや、大変な患者とは畢竟、救いがたく愚かしい私自身の鏡像にほかならないのだ。だから、我が身を憐れみ慈しむように、微力を尽くして懸命に引き受け続けねばならないのだ。
診療部長 栗田 篤志