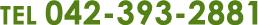備蓄米と健康
2025/06/04
5月に農林水産大臣が変わり、備蓄米がスーパーなどでも買えるようになりました。
お米が主食の私たちにとって、ふところ具合を気にせず“ご飯”が食べられることは、本当にありがたいことです。
そんな呑気なことを考えながら江戸時代の学者、貝原益軒の「養生訓」を読んでいると、“精白された白米は身体を弱くする。麦や雑穀を混ぜたほうが良い”とありました。
そうでした。白米ばかり食べていると「脚気(かっけ)」になってしまうのでした!
もっとも現代は副菜なしで白米だけを食べている人は少ないでしょうが、江戸時代は大都市「江戸」の上級武士や富裕層は白米をたらふく食べて「脚気」になり、下級武士や貧困層は麦や雑穀を食べて、「健康」だったようです。
これは「江戸わずらい」と呼ばれ、「江戸に長くいると足が立たなくなる奇病」と恐れられていました。
原因はビタミンB1欠乏症です。慢性的なアルコール依存症で発症する「ウェルニッケ・コルサコフ症候群」で出現する記憶障害や幻視もビタミンB1の欠乏によるものです。
ちなみに、ビタミンB12やビタミンB9(葉酸)が欠乏すると、妄想や被害感、抑うつ状態や認知機能の低下を引き起こすといわれています。
一時的には「認知症」を疑われることもありますが、欠乏を補えば症状は改善します。
「歯ぐきからの出血」が有名な「壊血病」はビタミンCの欠乏によるものですが、ビタミンCの欠乏は、思考の混乱や感情の極端な不安定さ、不眠などの原因にもなります。
また近年は、ビタミンDとうつ病、統合失調症、更にはASDとの関係も指摘され始めています。免疫や神経伝達物質、脳内炎症にも関係しています。
ビタミンDは食べ物から摂取すると同時に、日光に当たることで体内で作られるビタミンでもあることから、日照時間の減る冬に「気分が沈む」「やる気が出ない」などの症状のある場合は、ビタミンD不足を疑う必要があるかもしれません。
しかし誤解しないでください。ビタミンはたくさん取ればよいというわけではありません。
特に「脂溶性ビタミン」と言われる、(ビタミン)A,D,E,Kは身体に蓄積されやすく、中毒症状を起こし、腎機能や神経系が障害されることもあります。
「ドラゴンボール」に出てくる仙豆(せんず)とは違います。どれほどビタミンを取っても私たちはスーパーサイヤ人にはなれないのです。
お米も食べられるようになったことですし、一番大切なことは、バランスの取れた食事をして、朝日を浴びて、睡眠をしっかりとる。
これが一番健康によいのでしょう。
それが難しいのが、現代人なのでしょうが・・・。
副院長 野瀬 孝彦
人間関係って難しい(-_-;); コミュニケーションについて思うこと①
2025/05/28
もうすぐ傘寿を迎えようとしている歳になったというのに、いまなお、人間関係とはなんと難しいものなのだろうと思うことがある。人は一人一人異なった存在であり、外的体験は共有できるけれども、内的体験を共有することはできない。何人かの人が同時に同じものを見、同じことを聞いても同じように感じるわけではない。人が人とかかわるというのはその異なったもの同士がお互いに近づいていくということである。逆にまた、人が存在するということは、他者がそこに何かの意味を見出すなら、存在している人が意図しようとしまいと、何らかのメッセージは伝わっていくものでもある。
ずいぶん昔のことだが、ある患者さんから、「就職の面接にいくんだけど、いつものグレーのバッグと新しい黒いバッグのどっちをもっていったらいい?」とアドバイスを求められたことがある。いつものグレーのバッグは手垢などでかなり汚れている物だったので、面接ならば、きれいな黒いバッグのほうが印象がよいと考え、「黒いバッグの方がいいかなぁ…」と答えた。面食らったのは次の日のこと。彼女は面接の帰り道でコンタクトを無くしたという。そして「いつものバックなら無くすこともなかったのに、あんたのせいでコンタクトをなくしたのよ!!」と電話口で怒鳴りまくられたのである。
私は「私の意見を言っただけで、黒いバックにしなさいとは言っていない。どちらかを決めたのはあなたで、私に責任はない」といくら説明しても、相手には全く通用せず、しばらくの間彼女の怒りは収まらなかった。ぶちぶちと「坂田はそういういい加減な人間なのだ」と言い続けた。彼女の立場に立てば、恐らく、面接という緊張を強いられる場に出かけなければならないことで頭がいっぱいになっていたのだろう。自分で考えるなどということができなくて、私を頼りにし、全面的に私の判断に任せた。面接の緊張が続いたせいで、コンタクトレンズのことなど頭の中からすっかり消えていたのだろうとふと思い「ねぇ、あなた本当に黒いバッグにコンタクト入れたの?グレーのバッグ見てみた?」と言ってみた。彼女は、まさに我に返ったような感じで「え?」と聞き返し、しばらく間をおいて「あった」と小さな声で答えた。「ほら、みなさい」と言いたいところだったが私は「よかったね。じゃぁ、今日はゆっくり休んでね」と言って電話を切った。
多少「もやもや」が残ったままではあったが、「ま、いいか」と自分の心にけりをつけたと言うわけである。
看護部顧問 坂田 三允
春のつぶやき
2025/05/07
当院の前には大きなさくらの樹があります。
周囲のさくらの樹よりも早めに淡いピンク色になります。
今年もたくさんの花が咲き今では(4月中旬)葉ざくらになりました。
卒業式や入学式、入社式など出会いや別れ、新たな旅立ちなど私たちの生活の節目になる時期に欠かせないさくら。
こんなあわただしい時期に咲く…なのに、みんな立ち止まってさくらを見上げている姿はさくらに包まれ穏やかにみえるのです。
看護部長室長 緑川 雅
オスラー先生の3原則
2025/04/23
1849年のお生まれなので、ずいぶん古い方なのですが、ウイリアム・オスラーというカナダ生まれの内科のお医者様がいらっしゃいます。その方の「平静の心」という講演集があります。私はとても気に入っていて時々読み返すのです。
オスラー先生の3原則というものがありまして、それは何かといいますと、患者さんはどのような問題でやって来ているのかということを第1に、そして、それに対して私たちは何ができるのかということを2番目に考えて、3番目に、私たちがそのようにした場合、患者さんのこれからの人生はどうなるのかということを考えてから何かをなせということなのです。
患者さんはなんでここに来たのかっていうことを知るためには、聞かなければなりません。耳を澄ませて患者さんが言いたいことを聞き取らなければなりません。それは主訴として言葉になっていることとは全く違うことかもしれない。でも、その何かを見つけない限りは、私たちはそれに対して何ができるかを考えることはできないわけですね。ですから、言い古されたことではありますが、相手が伝えようとしているものに耳を澄ませてみようということ、また、患者さんと同じ目線で、同じ位置に立って、同じものを見る。同じレベルに立っているのだけれど、それから少し離れて一定の距離を保つということもとても大切なんだ、それが平静の心だとおっしゃっているのです。それは言葉を変えるなら、同情ではなく共感ということになるのかなと思うのです。でも、これが共感でこれが同情なのだと言葉で説明できるほど、私は達人でも何でもないのでうまく伝えられないのですが、いつもそうありたいと思っていることが、きっと大切なのかなと思っています。
次に何をしようかを考えることが始まり、私たちのすることが患者さんのこれからにどう影響を及ぼすのかを考えなければならない。例えば外科治療というのは、ある部分を取り除くことです。例えば胃袋の一部がない人を作り出すことですね。胃袋の一部がない人のこれからの生活がどうなるか。確かにがん細胞は取り除いたかもしれない。でも、胃袋のない生活をこの人はどうやって送っていくのだろうということまで説明し、その結果を考えた上で、私たちはその人に対して何かをすること。もちろん、理想どおりにすべてができるわけではないのだけれど、そういうことを考えないままに行ってはいけないことが、おそらくたくさんあるのだろうと思うのです。
看護部顧問 坂田三允
医者も病んでいる
2025/04/10
患者が病み、その家族も病むのと同様、医療者もまた病む。医師や看護師は自らを厳しく律して病気ひとつしない健康優良者であるかのような通念は、幻想に過ぎないと思う。
かのハリー・スタック・サリヴァンは、自らを予後の良い統合失調症と評したという。アイルランド移民の貧農としてアメリカに育った彼は、家畜が唯一の友という極限の孤独を潜り抜ける中で、精神の危機に陥った。後に伝説的な精神科医と仰がれる存在となったサリヴァンは、それゆえ思春期における同性間の親密な交流chumを、発病予防(レジリエンス)に欠かせない体験として重視した。その思想をもとに、同性看護師による小人数ユニットでの手厚いケアを実践し、まだ抗精神病薬のなかった時代に統合失調症治療において大きな成果をおさめ、独創的な精神医学理論を構築した(1) 。
あまたの選択肢から精神科へ導かれることは、おそらく偶然ではない。自ら心を病む、あるいは身近な他者が心を病むことを経験する等して、心の闇に強く巻き込まれつつ惹きつけられていく。あるいは、日々の臨床に身を浸すうちに、自らの心が蝕まれていったとしても何ら不思議はない。もとより深く精神を病む人間の治療に携わる業は、必然的に己が身を削るがごとき代償を課す。我が身を翻っても、予後の良い自閉症なのか予後不良のアルコール依存症なのかはさておき、操作的診断基準に照らし合わせれば、いくつかの精神障害に該当するかもしれない。ある者は飲み、ある者は搏ち、ある者は買い、市販薬をODする者も、自ら精神科ユーザーとなり投薬を受ける者も、秘密裡に自傷行為をする者もあろう。こうして我々は何とかして生き延びながら職務を全うする。しかし、不幸にして死を選ぶ者もある。一般と比してわが同業者の自殺率が高いことは、つとに知られた事実である。
精神の病いと限らない。私たちはおよそありとあらゆる病や災厄に陥る可能性を免れない。うつ病にも、統合失調症にも、認知症にも、心筋梗塞にも、癌にも、肺炎にも、不慮の事故にも、自然災害にも。堕した己を再び顧みれば、健診を受ける度に高血圧、肝機能障害、メタボリックシンドローム等と指弾され要治療と突き付けられるが、所詮はこんなものよとうそぶき、医者の不養生よろしく内服もままならない。ちなみにサリヴァンは、臨床的・学問的に大きな功績を残した後、世界会議の重責を果たすための渡航中、脳卒中により57歳でパリに客死した。
対岸の火事ではない。やはり、すぐにでも節制をせねば。1人でも多くの患者を救うために健康で長生きせねば。ジムに通ってエクササイズに励まねば…。いやいやいや、そうは問屋が卸さない、が本稿の論旨だった。おいそれと聖人君主にはなれず、日々大小の病を抱えながら生きざるをえないことにおいては、患者も医者も大同小異である。だからジムなどはやめにして、いざ酒場へゆかん。そしてしたたかに酔い、激務の澱を洗い流そう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1)中井久夫 2012 『サリヴァン、アメリカの精神科医』みすず書房
診療部長 栗田 篤志
新しいことに挑戦するとき(基盤をしっかり学ぶ)
2025/03/21
新しい治療法や援助論がたくさん出てきています。それに挑戦していくことはとても大切なことだとは思いますが、それを取り入れるときに気を付けていただきたいと思うのは、それが生まれた背景やその基盤となっている理論などをきちんと学ぶということです。
少し前に、気分障害の新しい治療法について書いていただこうと依頼した医師から「看護の本にこういうのを書くと看護婦さんが寄ってきて、どうするのですかと方法だけを聞きに来る。うるさくてかなわない。だから、書かない」と言われたことがあります。
方法というか技法というのは、ある意味で手順です。手順を知ることで分かったような気になり、やってみようとしてはいけないのだと教えられました。変わってはならないということではなく、どんどん取り入れていってほしいのですが、基本はしっかり学ぶという姿勢を変わらずに持っていることが大切なのだと思います。
看護部顧問 坂田 三允
感染症とロシアウクライナ戦争とナイチンゲール
2025/03/05
昨年末はインフルエンザが急速に猛威を振るい始め、更に新型コロナウイルス感染症の第12波(?)の兆しが重なり、医療機関はどこも戦々恐々として新年を迎えました。
幸いなことに、手がつけられないほどの感染拡大とはならず今に至っています。
海外に目を転じると、今年初めにアメリカではトランプ氏の新大統領就任式がありました。好き嫌いは抜きにして、TVでこの人を観ない日はありません。“戦々恐々”として、観ているのかもしれません。
ここのところは、この新大統領がロシアウクライナ戦争を終わらせようとする動きに世界中の関心が集まっています。すでに両国で10万人以上の命が失われている戦争です。
それはさておき、ウクライナに属していたクリミア半島は10年ほど前にロシアに編入され、この時以降を、ウクライナ紛争と呼んでいました。
それもさておき、ここで私の関心は1854年の「クリミア戦争」と、この戦争で「白衣の天使」の象徴となったナイチンゲールへ一足飛びしてしまうのです。
歴史上の人物伝として、近代の偉大な女性として、フローレンス・ナイチンゲールの名前を知らない人はいないでしょう。
しかし、本当のナイチンゲールとは、どんな天使だったのでしょう?
ナイチンゲールは言います。「天使とは・・・・・人が忌み嫌う仕事を、感謝されることなく行う者である」英国女性の厳しい口調が響いてくるようです。
彼女が砲弾飛び交う戦場で、献身的に、自己犠牲を惜しまず、敵味方の差別なく看護した・・・などという事実はないようです。
伝説となった偉人というのは、その時代が抱く偶像として伝説となるのでしょう。
わが子を愛するように、どんな苦労もいとわぬ優しい母性で病める者に手を差し伸べる天使。この時代はそのような女性看護師に、ナイチンゲールという名前を付けたのでしょう。
時の流れはこのようなナイチンゲール像は虚像であると教えてくれます。しかし、これが虚像であることはナイチンゲール自身が一番よく知っていたようです。
彼女が派遣されたイギリス軍の陸軍病院の病棟は目を覆いたくなるほどの不衛生な環境でした。床はトイレからあふれた汚水に浸され、動物の死骸も下水からあふれている状況だったといいます。
クリミア戦争では、10万人ほどの英国陸軍のうち、約2万人が死亡し、そのうち約1万6千人は戦闘によってではなく、病院内で感染症で亡くなっていたのです。彼女はこの現状を母国に報告し、病院内の清潔を徹底し、換気を命令し、ギュウギュウ詰めだった病棟でベットの間隔をしっかり空け、密な状態を解消しました。まさに、現座の感染予防対策そのものです。「細菌」が発見される以前の話です。・・・詳しくは、またの機会に。
現代のナイチンゲールのプロフィールは、「近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母」となっています。虚像でも、偉人だったのです。
副院長 野瀬 孝彦
傍らで共にあること
2025/02/19
うれしい体験もありました。何か行為をして、それが患者さんにとってほんとによかったのかどうかということはなかなか確かめることができません。精神科でケアを評価するのはとても難しい。患者さんは喜んでくれるわけでもないし、「何しに来たのよ、あっち行ってよ」なんて言われながらその場にいることだって必要なわけですから。そんな中で、長い六十何年の間で唯一の体験だと思うのですが、とても患者さんに感謝された体験があります。
その人はボストンバッグ抱えてホールに出てきて、ボストンバッグの中のものをまき散らし始めました。しばらく「なんでこんなことをしているのだろう」と思って見ていたのですが、なんとなく彼女のそばにいってみようかなという気持ちになったので、横に座って患者さんが放り出したものをたたんで重ねていくという作業を無言で続けました。彼女が広げる、私がたたむということを3、4回繰り返したあと、最後に私がたたんだのをボストンバッグに詰めて彼女は部屋に戻っていきました。なんだったのだろうとずっと思っていたのですが、分かりませんでした。2年か3年たってからのことです。外来でバッタリ彼女に会いました。そうしたら「坂田さん」って抱きついてきて「坂田さん、あのとき一緒にいてくれたよね。うれしかったよ」と彼女が言うのです。一言も話していないんです。お互いに。ただ、無言で出して入れて、出して入れてということを繰り返していただけなのです。
そのときに、言葉じゃないんだということがすっとわかったのです。存在、そばにいること、ともにあることの意味のようなものでしょうか。そのときのことは、なかなか言葉では表現できないのですが、何かそこにいてあげたくなって、いることが苦痛ではなくて、最初の始まりは「なんでこんなことするんだろう」という思いでしたけれど、そのやりとりをしている間、不快でなかったことは確かです。彼女が快であったかどうかは分からなかったのですが、その彼女の一言を聞いて、あのときやっぱり彼女も不快ではなかったんだっと分かって、こちらが不快じゃないときというのは、もしかしたら相手も不快じゃなくいてくれるときなのかもしれない。そういう2人がともにいることで時間がつぶせたら、それはそれですてきなことかもしれないということを学びました。ですから、コミュニケーションは言葉ではないということもとても大事なことのような気がしています。
看護部顧問 坂田 三允
院内感染対策のこと
2025/02/05
新型コロナ(COVID-19)の流行があり、普段から病院の面会や外出等に制限をもうけている病院が多くなっています。当院も実は、若干ですが時間等の制限をしています。これがおかしいという議論はあり、一理あります。あまり外部との交流を持たず、入退院も少ないような精神科病院で、コロナを口実により一層閉鎖性を強めているところがあり、そういうのは大きな問題です。しかし、面会が感染症を持ち込まれる契機の一つであることは確かです。これまで当院は何度もクラスターを経験しています。その多くは原因が不明で、推測できるもののうち一番多いのは職員由来、次が入院患者さん由来で、面会者からと思われるものは少ないですがやはりあります。
クラスターは、コロナに不顕性感染や潜伏期、検査での偽陰性等があることで、やむを得ないところがあります。しかし、一度これが起こると、患者さんたちを危険にさらしますし、行動の制約も伴います。職員にもうつりますので、勤務者が減り、病棟業務に支障が出ます。入院をお受けできなくなると、いざというときに頼ってきてくださっている地域の方にも迷惑が掛かります。病院の経営としても、膨大な物品や廃棄物処理が必要になり、支出が増えます。できるだけ予防したいというのは正直なところです。
しかし、当院は、入退院についてはできるだけ止めない、というふうにやっています。クラスターの真っ最中は入院も退院も制限せざるを得なくなることがありますが、それ以外はなるべく制限せず、特に退院のために必須であるような外出・面会・会議等は行うようにしています。今後も皆さんのご要望をお聞きしつつ、よりよい方法を検討していきます。何卒ご理解・ご協力をいただきたく、この場を借りてお願い申し上げます。
院長 中島 直
生きていくにはゴミ箱が必要不可欠(愚痴は心の生ゴミです)
2025/01/22
暇をつぶしに来ていた彼女は3年、4年ぐらいたった頃「ごめんね、いつもごみ箱にして」と言いました。暇つぶしからごみ箱に昇格したようです。そのときに思ったのです。「ごみは捨てなきゃいけない」と。グチというのは心の生ごみだと思いました。生ごみをため過ぎたら発酵して爆発します。そのようになる前に捨てなければならない。こまめに捨てることが必要で、受け取る側のごみ箱は間口が大きくなければいけないとも考えました。間口が小さいと本人は捨てたつもりでも、ごみ箱の周りに散らかってるだけということになりかねない。だから、大きな間口のごみ箱でいるということがとても重要なのだと彼女から学ばせてもらったのです。捨てるということは、身の回りを整理することですからすっきりします。ごみ箱は返事などしません。黙ってただ受け取るだけです。受け取るというよりも、来るを拒まず立っているだけといったほうがよいかもしれません。でも、そういう存在も必要なのだということも学ばせてもらったと思っています。
看護部顧問 坂田 三允