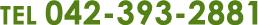処方が間違っている
2025.09.05
精神科薬物療法は根拠のない出鱈目が多く、節操のない多剤多量処方による薬漬けが横行している、という非難が昔も今も方々から寄せられる。あながち事実無根の誹謗中傷ではないと感じる一方で、多くの精神科医はそこまでひどくはないですよ、とか、大変な患者の薬剤調整は一筋縄ではいかんのですよ、とつい言い訳が漏れ出そうにもなる。
この手の糾弾を浴びるのはひとり精神科医のみであり、他科の医師にはほとんど無縁ではなかろうか。むろん、どの科においても診断や病態を捉え損ねて薬剤選択を誤る、ということはあろう。無知に基づく誤りやバイアスによる逸脱は論外として、精神科においては診断や病態を正しく評価できていてもなお、薬剤選択や処方量がおかしくなることがありうることは、特筆すべきだろう。知識も経験も豊富なひとかどの精神科医にあっても、時として、処方変更を繰り返して一向に定まらない「彷徨的処方行動」1に陥り、患者が要求するがままに処方し続ける「白衣を着た売人」2に堕すことがありえるからには、事はそう単純ではない。
我々が処方する向精神薬が、主として精神症状を標的とし、脳=中枢神経系を媒介して心=体験世界を変化させる薬理作用をもつことは、その原因のひとつかもしれない。この構造ゆえ、効くと思い込めば効く(プラセボ効果)、効かぬと思い込めば効かぬ(ノセボ効果)、の主観的変数が大きく介在せざるをえず、患者のみならず治療者も、精神行動上の変化を主観的・間主観的に捉えて評価するほかなく、身体科薬物療法ような血液検査や画像による客観的な効果判定は不可能に近い。よく効きました、という安堵の表情を見れば少量単剤で済むものが、全然効きません、という焦慮の表情が続けば多剤多量に流されかねない。重い精神病症状や逸脱行動が遷延すれば、医師の焦りから無差別爆撃的な多剤高用量処方を招く恐れもある。
それがゆえにか、精神科医は向精神薬を単なる物質として患者に投与するのではなく、意識的にであれ無意識的にであれ、様々な想いを言葉とともに薬に乗せて差し出すようになる。それは、少しでも良くなりますようにという願いや祈りであることがほとんどだが、時には、いい加減にしてくれという陰性感情のこともあろう。薬物療法家の立場からすれば、こうした心理的夾雑性はできる限り排したいだろうし、精神療法家の立場からすれば、逆に薬という物質的夾雑性を邪魔に感じるかもしれない。しかし、実地臨床においてはあくまで両者のアマルガムしかありえない。
このことは、医師-患者の関係性そのものが薬効に大きな影響を及ぼすことにも通じる。身体治療と比較すればわかりやすい。例えば外科医であれば、いかに愚劣でも手術の腕前が超一流の方が、人格者ではあるがぶきっちょで手術下手よりも、明らかに治療的と言える。一方、精神科医であれば、少なくとも患者から信を置かれるに足るだけの誠実さや礼容等、その人間性が治療に少なからぬ影響を及ぼし、ひいては薬効をも左右する。安定した治療関係では処方はシンプルかつ少量に傾き、不安定な治療関係では多剤多量に傾きやすい。
さらに、精神科薬物療法は医師から患者へと一方的に投与されるものではなく、医師と患者が共同作業により産み出していく合作、という含みが強くなる。アレでもないコレでもない、と二人三脚で長い時間をかけて作り上げた処方レシピは、医師の存在とも相俟って、患者にとってなくてはならない支えとなる。さながら、長年連れ添った妻の手料理が、夫の日々を無言の裡に支えているように。
反対に難渋する治療においては、こじれた夫婦関係のように、いくら対話を積み重ねても軋轢が修復できず、溝が広がることもある。気づいた時には、患者もろとも多剤大量処方の海の中へ投げ出され、漂流している。そしてある日、増えども増えども一向に改善しないことに絶望した患者がオーバードーズし、救命救急外来に運ばれる。情報提供を求められた主治医は、自らの手による破廉恥極まる処方にあらためて直面し、愕然として天を仰ぐ。後日、患者にとっては行きずりにすぎない精神科医がコンサルテーションした結果、見事に減薬されてエレガントな処方となり、憑きものがとれたようにすっきりとして舞い戻ってきた彼女と対面した主治医は、茫然として再び天を仰ぐ。
だから、そのような処方を見つけたら、どうか勇気をもって声を上げてほしい。「センセー、その処方は間違ってます!」と。
副院長 栗田 篤志
1 中井久夫 2000 『中井久夫選集 分裂病の回復と養生』星和書店
2 松本俊彦 2021 『誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論』みすず書房
(1895字)