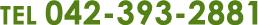家族も病んでいる
2025.01.08
患者の家族も、しばしば精神を病む。確かに患者自身も病んではいるが、負けず劣らずその家族も病んでいることがある。さらには患者として連れてこられた当人よりも、連れてきた家族その人こそが病んでいることも稀ならず経験する。考えてみれば、これは精神科に特有の事態かもしれない。例えば、骨折して整形外科を受診した患者よりも、その家族の方が重症の骨折だった、なんてことはおよそありそうにない。あるとすればせいぜい、感冒の子を受診させた親も同じウィルスに感染していた、という程度だろう。ただし感冒の場合、感染が判明してなおそれを否認する家族は少ないだろうが、自らも精神を病んだ家族は、その病状が重いほど病識を欠く。ここに、精神科患者の家族が精神疾患を病む固有の困難があると同時に、関係の病たる精神疾患の本質も垣間見える。
家族心理学にIdentified Patientという概念がある。直訳すれば、(家族の中で)患者として特定された人、だが次のような含意がある。病むのは家族なるシステムそのものであり、家族病理から析出された偶然の結ぼれとして患者があるにすぎない。だから家族療法は患者のみでなくその家族成員すべてを治療対象とする。これを敷衍すれば、病んでいるのはむしろ社会であり、患者は社会病理の犠牲者(スケープゴート)である、だから患者の治療よりも社会変革こそなされるべき、の思想に至る。反精神医学とよばれるこうしたラディカリズムが精神医学界を席巻した時代が、かつて本当にあった。確かに私たちも、控えめに言って患者よりも狂っているとしか思えない地域社会や行政と、日々闘っている。あくまで患者を護るためであり、社会を変えるのが目的ではないけれど。
さて、では深く病む患者家族と、私たちはどのように付き合えばよいのか。これが実に悩ましく難しい。病識なく拒絶的な重症患者に対する治療の方途を、精神医療はその長い歴史の中で培ってきた。しかし、病識なく拒絶的な重症家族にどう処するか、の知識や技法を私たちはほとんど持ち合わせていない。病んだ家族と折り合えなければ、結局は患者の治療も失敗に終わる。
精神科臨床における諸事象の多くがそうであるように、おそらくこの問いにも正解はないだろう。ただ、ひとつ言えることがあるとすれば、いかに病理の深い家族でも、患者にとっては嘆かわしくも不可避的で代替不能な存在ということだ。家族という閉じられた二者関係において、傷を抱えぬ者などいようか。殊に重い傷を抱えた家族に他者が踏み込まざるをえない時、手痛く返り血を浴びることもあろう。他ならぬ私も、多くの血を浴びてきた一人である。それでもなお、重症家族をいかに手当てすべきか、今も問い続けている。
診療部長 栗田 篤志