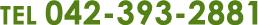接遇・沿革
接遇
接遇を重要なこととする意義について
以下の文章は、理事長が職員に向けて、接遇の意味合いを書いたものです。当院でも、接遇について委員会を立ち上げ、徹底させる努力をしているところです。
医療とは、医療技術の提供によって、人間(患者さん)の病気の治療をもたらすことが中核的な仕事です。
精神疾患は、いつも生物学的な側面、心理学的側面、社会的側面の三つの方向から考えて対処する必要があります。
生物学的な側面とは、狭い意味での医学的な面で、統合失調症を脳の伝達物質の不調としてとらえるようなものです。
心理、社会的側面は、その人が過去に生き、現在に生きている人生が、未来においてどのようになる(する)のか、という不安のなかでとらえることが重要であることを意味しています。
生物学的失調は、この根源的不安の生物学的表現と考えることも可能です。
ところで、人間における心理、社会的側面とは、その人が持つ①自分と自分との出会い方(の失敗)と②自分と他人との出会い方(の失敗)の複合としてもとらえることができます。
自分との出会いは、他人との出会いと、お互いの密接に関係しています。
人間とは、生まれてから、死ぬまでの間の一生の時間の中で、自分の身体を通して、男とか女、年齢に応じて、家族や社会の中での役割や、人間的な関係との中で生きています。
統合失調症は、社会的関係の病と言われています。感情障害は、気分や情動の病と言われています。境界例は、二人関係の病として特徴を持っています。
発達障害は、結局、人間的情緒的なコミュニケーションの不調を特徴としています。認知症は、記憶や認知の老齢化に伴う脱落変容です。
病院とは、一般社会から病という苦難を持ってきた人間のアジール(避難所)の意味を持っています。
患者さんは、自己そのものに傷つき、社会や他人との関係に傷ついて、人間という時間の迷宮にはまり込んで、病院に来たのです。
病院は、「そのような人々」を、「病を持つ人」として、「その病を治療しケアをして社会に返す」のが仕事です。ところが、精神疾患とは、上記のようなものとして考えられるのであるから、病をその人から切り離して対処することができません。その人そのものを、相手に仕事をするのです。
人(私たち)が病に傷ついた人に、どのように対処するかが接遇です。
私たちは、様々な職種によってなりたっています。職種によって、要求される事柄が異なっています。
病を「どのように理解するのか」「病んでいるその人は、どのような困難を持っているのか」「その人は何故、そのような振るまいや、行動(時には逸脱行為)を取るのか」、一々説明ができないことのほうが多いのですが、病院は基本的にそのような人を大事な宝を包み込むような役割を持っているのです。
接遇とは、病院の仕事の全体を包括しているのです。
看護の仕事は、その中でも「接遇」の中核を背負っています。
看護の仕事は、接遇という言葉ではとうてい表せないような意味を持っています。
精神科の患者は、その多くが、強制入院や様々な行動制限を、その保護のために、その宝ものとして扱うべきその人に対して、私たちが行う必要性を持っています。
その実行者も看護です。
沿革
| 1984年 | 北久米川病院開院 |
|---|---|
| 1997年 | 医療法人化 リハビリテーション部新設(OT・小規模DC開始) |
| 1999年 | 多摩あおば病院に名称変更(12月) |
| 2000年 | 新病院完成 療養病棟2単位 DC:大規模(6月) |
| 2002年 | 新看護3:1 DNC開始(NC枠20名から30名へ) |
| 2004年 | DC:大規模70人枠 |
| 2007年 | 精神科急性期治療病棟2 |
| 2010年 | 精神科急性期治療病棟2→1 |
| 2012年 | 精神科救急1 |
| 2013年 | 依存症プログラム開始 物忘れ外来開始 児童思春期外来開始 |
| 2014年 | CT導入(6月) |
| 2015年 | 認知症疾患センター連携型 |
| 2016年 | 精神科急性期医師配置加算算定開始(8月) |
| 2017年 | 東村山市認知症初期支援チーム指定 外来管理棟完成 6診→9診へ |
| 2018年 | 精神科専攻医研修基幹型施設 クロザリル入院治療導入認可 電子カルテ導入 |
| 2019年 | 小平特別支援学級武蔵分教室「風の学校」開校(2月) |
| 2022年 | 児童・思春期病棟(3月) 外来診察室を9診→10診へ(9月) |
| 2023年 | 東京都から依存症専門医療機関(アルコール健康障害)の選定(3月) 院長交代:中島直が院長就任、木村一優が副院長就任(6月) |